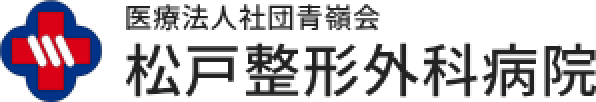肩学会開催への挑戦と、その舞台裏
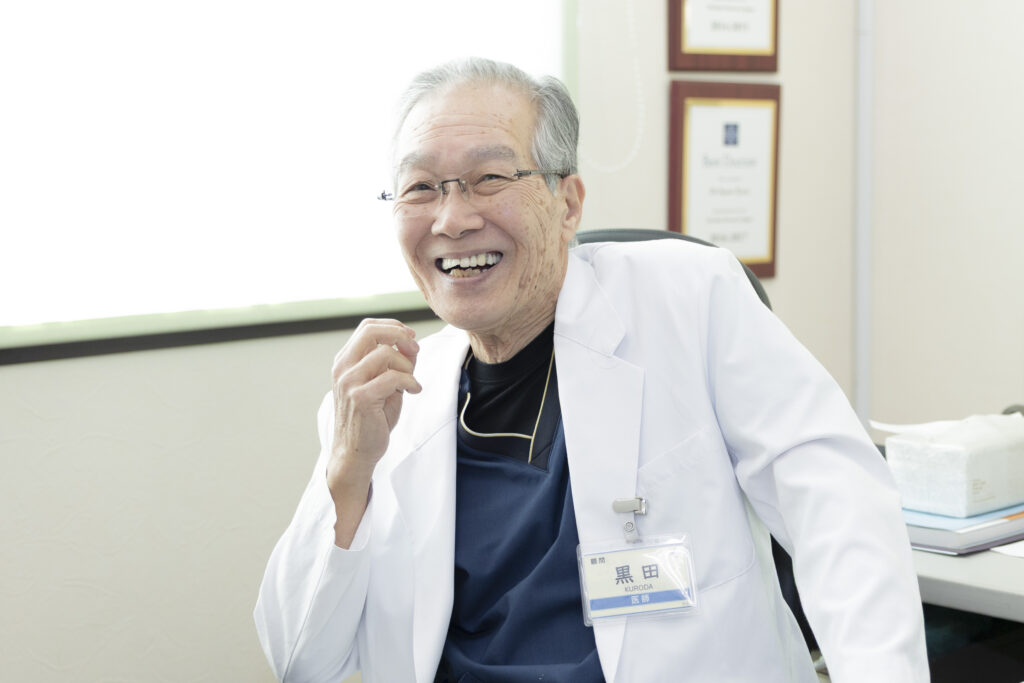
2005年に第32回日本肩関節学会をディズニーリゾートで開催しました。
その際、私は「学会屋を入れずに学会を運営したい」と考えていました。この話が学会屋の耳に届き、「できるものならやってみろ!」という挑発的な言葉が私の耳に入ってきたため、「それならやってやろう!」と決意し、自ら運営することになりました。もともと、主催者が努力すれば学会屋は不要だと考えていたからです。
しかし、実際に運営を進めると多くの困難に直面しました。学会屋を頼めば良かったと思ってしまうほど大変でしたが、多くの方々の協力を得て、学会を無事に成功させることができました。事務局の秘書を娘がやってくれ、夜遅くまで尽力してくれたほか、当日は娘と石毛先生がインカムを付けて会場を走り回り、裏方には家内や伊東先生の奥様、友人たちが協力してくれました。
また、当院の電子カルテを作成してくれた新世紀(現在はAPOSTRO)の方々にも技術面で手伝っていただきました。特に大変だったのは演題の選考でした。現在では応募された演題はほぼ全て採用するのが一般的ですが、私の学会では抄録を審査委員会で選定し、約70%しか採用しませんでした。そのため参加者数が減少し、収入が減るリスクがありましたが、住吉先生の「500万円ぐらいの赤字は大丈夫だよ。病院から出せるよ。」という言葉で精神的に救われました。
最終的には赤字を出すことなく、学会を成功させることができました。演題を絞ったことで、一つの発表に十分な時間を確保でき、ディスカッションの時間を長く取ることができました。例えば、6分間の発表に対して7分間のディスカッションを行い、パネルディスカッションではさらに長い討論時間を設けました。このように討論を活発化させることを目指した学会運営は非常に有意義でした。
肩関節学会が肩関節研究会と呼ばれていた時代は、整形外科学会の中でも最も議論の厳しい学会でした。私が初めて演題発表をした際に、質問攻めに遭った経験が強く印象に残っています。その雰囲気を再現できたことは、非常に満足のいく成果でした。ただし、学会終了後は達成感以上に疲労感が強く、「もう二度と開催したくない」というほどの大変さでした。(笑)
学会発表を支えたデータの力

データが多ければ多いほど、精度の高い分析結果を得ることができる――
このことを、私は長年の経験を通じて痛感してきました。開院と同時に私がデータ収集を始めた頃、コンピュータなど存在せず、頼れるのは穴の開いたパンチカードだけでした。カードに針金を通して必要な情報を抽出するという、気の遠くなるような作業。
100枚を超えるカードを扱うと、それはもう途方もない手間でした。
しかし、時代は進み、コンピュータが登場しました。すぐに導入し、データ処理に活用しました。それでも、毎日のデータ収集と入力に多くの時間がかかり、毎日の業務が終わってから約2時間を費やす日々。肩に関する紙カルテを研究室へ運び、一枚一枚慎重に入力する、そんな地道な作業を続けていました。
データが積み重なるにつれ、学会発表のテーマに合わせた情報を瞬時に抽出できるようになり、母集団45,000例で統計を出すと、誰も反論できなくなるほどの説得力を得ました。かつて何日もかかっていた学会前のデータ抽出作業は、今や約30分で完了します。それは、長年の努力と技術の進歩がもたらした大きな変革でした。